つくば市の学習塾「あかつき塾」 | ネット・オンライン授業で筑波大学を目指す

050-3577-9014
営業時間:10:00~22:00
定休日:日曜日

050-3577-9014
営業時間:10:00~22:00
定休日:日曜日

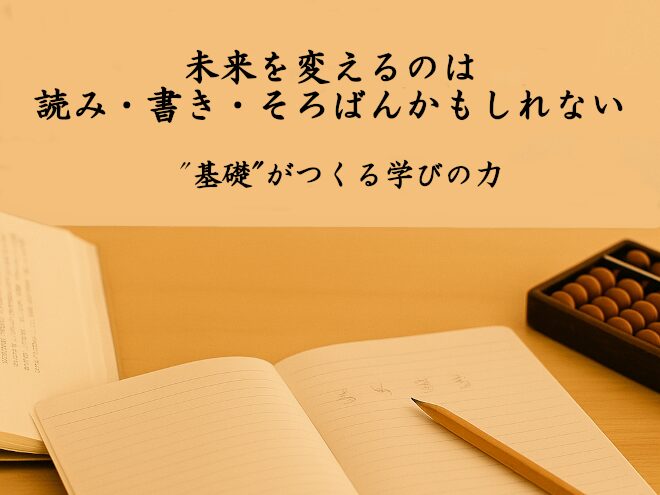
Contents
「学力が低下している」。
そんな言葉をニュースや記事で見かけるたび、私はある違和感を覚えます。
本当に“学力”が落ちているのか? それとも、“普通”の基準そのものが変わってしまっただけなのか?
私は決して特別な教育を受けてきたわけではありません。小学生の頃から、読み書きそろばんといった基礎的なことをしっかりと積み重ねてきただけ。成績も良かった方だとは思いますが、自分を“特別に賢い”と感じたことはほとんどありません。むしろ、「これは普通のこと」と思ってやってきました。
けれど今、その「普通」が崩れ始めているように思えてなりません。
子どもたちの学習における“前提”が変わり、学びが積み上がらなくなっている。
この記事では、「普通」の価値を見つめ直し、もう一度、学びの根本に立ち返る必要性を語りたいと思います。
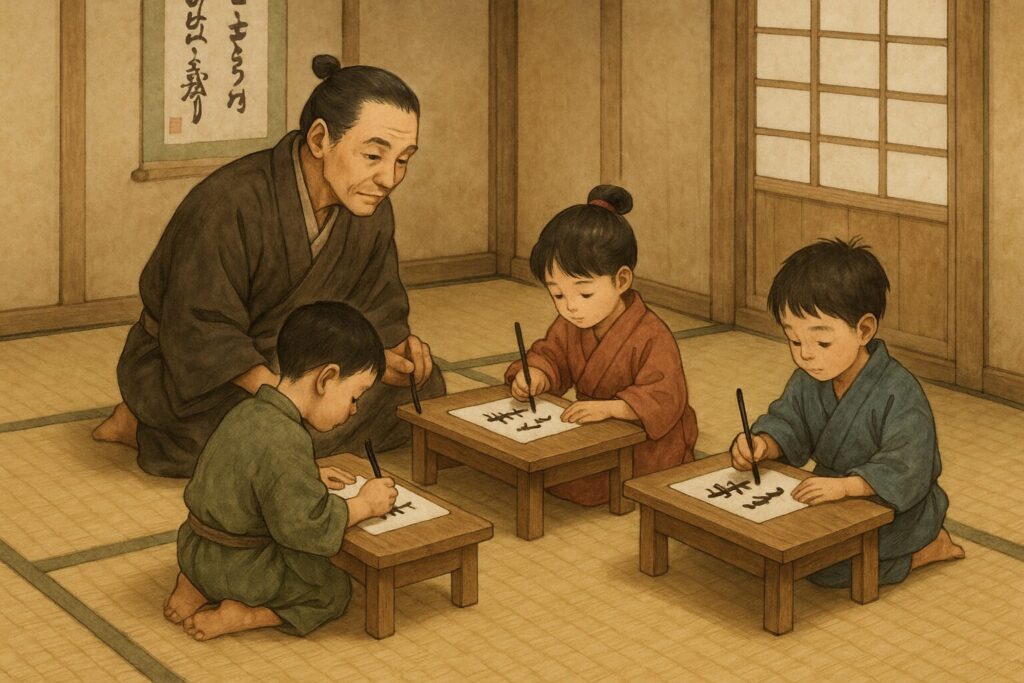
※画像はイメージです
教育の「普通」を考えるうえで、私はよく江戸時代の寺子屋のことを思い出します。
当時、日本の庶民の識字率は世界的に見ても高く、1800年代の江戸では男子の識字率が70%を超えていたという推計もあります。寺子屋は、武士だけでなく農民や町人の子どもたちも通える庶民的な学び舎でした。
教本には『往来物』と呼ばれる実用的な手紙文や商売文書が使われ、計算ではそろばんと算盤帳が用いられていました。これらは日常生活に密着しており、単なる教養というよりは「生きる術」として学ばれていたのです。
このような「基礎の充実」があったからこそ、明治の急激な近代化に民衆がついていけた。近代国家としての土台は、すでに江戸期に築かれていたという見方すらできるのです。
現代は、ICT教育やアクティブラーニングの導入が進む一方で、「手で書く」「声に出して読む」「数字を暗算する」ような基本動作が軽視されがちです。しかし、だからこそ今、「原点に戻る」必要があるのではないでしょうか。

私は子どもの頃、そろばん教室に通っていました。
文系の私にとって、数学は得意ではありませんでしたが、そろばんだけは不思議と好きで得意でした。珠をはじくリズム、数字のパターンを頭に浮かべる感覚、それを繰り返す中で自然と計算力が鍛えられていきました。
そろばんの練習では、ただ数字を計算するのではなく、問題を頭の中にイメージとして思い浮かべ、無意識に処理していく。これが身につくと、学校での計算問題が「視覚的に理解できるもの」に変わりました。
そして得られたのは、単なる計算スピードではなく「脳の処理力」。
それは、文章の構成力や論理の組み立て、問題解決能力にもつながっていきました。
実際、近年の研究でも、そろばん学習を通じた前頭前野の活性化や、ワーキングメモリ(短期記憶)力の向上が報告されています。
「基礎の反復」は、思考を支える筋肉――まさに“脳の筋トレ”だったのです。

学びには、“点”が“線”に変わる瞬間があります。
それまでバラバラに見えていた知識が、あるときふとつながって一つの流れになる。私は中学生のとき、数学の証明問題に初めて真正面から取り組んだときにその感覚を味わいました。
最初はまったく意味がわかりませんでした。でも、そろばんで身につけた計算力や、日々のノートで培った整理力が、気づけば“応用力”へと変わっていました。
これは偶然ではありません。
基礎という“点”をしっかりと積んでいたからこそ、“線”としてつながった。
そしてその線が、さらに“面”へ、“空間”へと広がり、学びの世界を拡張していくのです。
この「点が線になる瞬間」を迎えるためには、やはり最初に十分な点を打っておく必要があります。
子どもたちが未来の学びに羽ばたくには、その“助走距離”が必要なのです。

では、なぜ現代の子どもたちには、その「線につながる」経験が乏しいのでしょうか?
一因は、教育の現場において“普通”の基準が下がっていることだと感じています。
かつては小学生でも自然にできていた九九や音読、漢字の書き取りが、今では「難しい」とされ、補助教材や支援指導の対象になるケースも珍しくありません。
また、文科省が参加しているPISA(学習到達度調査)では、日本の生徒の読解力が2018年に大きく下がり、世界的にも注目を集めました。
もちろん、楽しさや個性を尊重する教育も大切です。ですが、「基礎があるからこそ楽しめる」「共通の土台があるからこそ個性が生きる」という前提が抜け落ちると、教育全体が“宙に浮いた”ものになってしまいます。

私は今でも思います。
自分は決して“優秀”ではなかった。ただ、「普通のことを普通に続けてきただけ」だと。
でもその“普通”が、後にとてつもない力を生んだ。
学びを深めることができたのも、論理的に思考し、他人に伝える力を磨けたのも――全てはあの時の“読み・書き・そろばん”があったからです。
今こそ、もう一度この「普通」の再定義が必要です。
AI時代、情報爆発時代にこそ、基礎が“武器”になる。だから、子どもたちにはそれを「当たり前のように使える自分」であってほしい。
教育とは、未来の誰かのために“残していく”ものです。
それは自分に返ってくる利益ではなく、社会に根を張る“持続可能な文化”のようなもの。
だからこそ、リターンを求めてはいけない。むしろ、リターンがなくても継続できるほどの“価値”が、教育にはあると信じています。
“普通”の底力を信じ、取り戻すこと。
それこそが、未来を変える確かな一歩なのだと、私は信じています。

山本剛義
茨城県つくば市在住。オンライン学習塾「あかつき塾」塾長。公共事業・環境整備・清掃業・ビルメンテナンス業・警備業など幅広く事業展開。子どもたちへの基礎学力支援をライフワークとし、「読み・書き・そろばん」の重要性を提唱している。