つくば市の学習塾「あかつき塾」 | ネット・オンライン授業で筑波大学を目指す

050-3577-9014
営業時間:10:00~22:00
定休日:日曜日

050-3577-9014
営業時間:10:00~22:00
定休日:日曜日

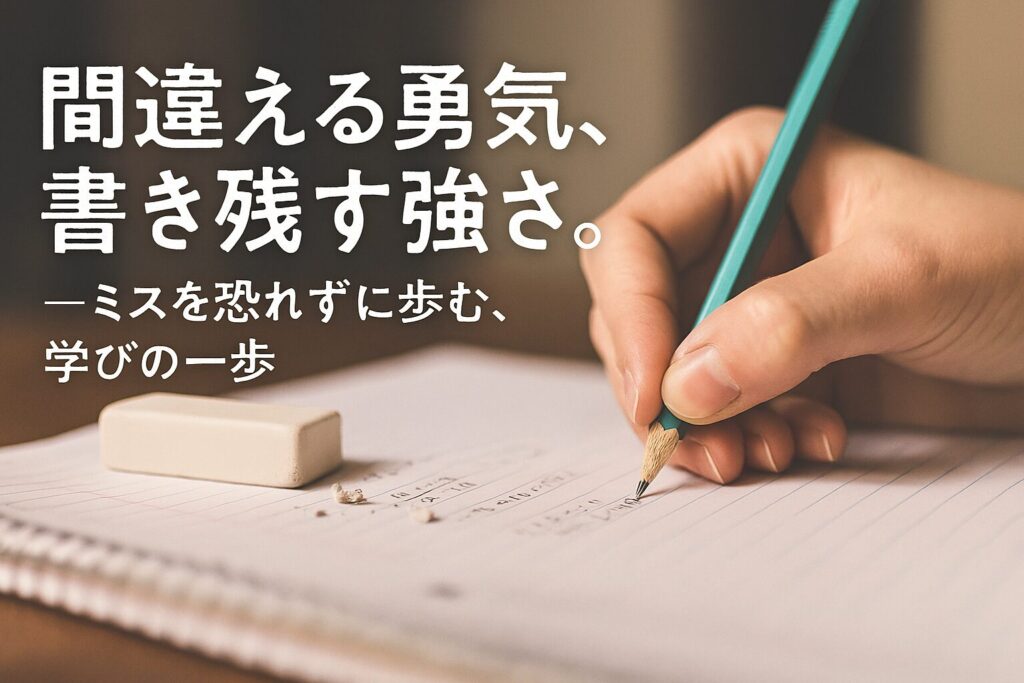
Contents
「なんでこんなミスしたの?」「また間違えたの?」
そんな言葉を、私たちはつい口にしてしまいます。子どもたちもまた、テストのたびに「間違い」を“減点”や“恥”として受け止めます。でも、“ミスは悪いこと”という思い込みが、いつのまにか学びの芽を摘んでいるとしたら——。
テストの点数が悪かったとき、「わからなかった」よりも「わかっていたのに間違えた」の方が、子どもにとってはショックが大きいものです。なぜならそこには、**「自分がダメだった」**という感覚が強く刻まれるから。
つまり、「間違える=自分を否定される」と受け取ってしまう。ここが、**学びと自己肯定感を切り離してしまう“心の分かれ道”**です。
学校でも家庭でも、ミスはどうしても“結果”として目につきます。けれど本来、学びとは**「分からない→理解する→できる」までのプロセス**。その途中には必ず「間違い」が含まれています。
むしろ、間違いこそが「わかっていない箇所の可視化」です。見つけたミスは、“修正可能な弱点”が目の前に現れたサインとも言えます。
にもかかわらず、ミスを責められることで、子どもたちは「正解だけを出すこと」をゴールにしてしまいがちです。これは“正解主義”という名のプレッシャーです。
私たちは、子どもに「間違えたって大丈夫」と言えているでしょうか?ミスを責めるより、「ここが伸びるチャンスだよ」と伝える視点があれば、子どもたちの学び方は、もっと自由で、前向きなものに変わっていきます。

「ここ、なんで空欄なんだろう?」
テストや課題を見返していて、そう思うことはありませんか?子どもたちの中には、「間違えたくないから空欄にする」という選択をとる子が少なくありません。実はそこには、“ミスをしたくない”という強い自己防衛の心理が隠れています。
子どもにとって、間違えることは怖いことです。「違う」と言われるのが恥ずかしい。
「なんでこんな答え書いたの?」と責められるのがつらい。だから、「書かなければ間違いにはならない」という論理で、空欄にするという“逃げ”を選ぶ。その気持ちはとてもよく分かります。
けれど、空欄には“ミスの痕跡”が残らないという大きな問題があります。何を考えていたのか。どんなところで迷ったのか。本来なら、そこに子どもの思考の“軌跡”が残るはずなのです。
仮に間違った答えであっても、そこには価値があります。「なるほど、こういう勘違いをしていたのか」、「視点は合っていたけれど、途中でずれてしまったんだな」と私たち指導者も、保護者の方も、そして子ども自身も“間違え方”から多くのことを学べるのです。
正解か不正解か、それだけで判断されてしまう環境の中では、「間違うくらいなら書かない」が合理的に見えてしまうのも無理はありません。でも、それは本当にもったいないことです。書かないことで、次の学びへのヒントが消えてしまうからです。
私たちはこう考えています。
“正解を書く”より、“自分の考えを残す”ことの方が大切な場面があると。
だから、あかつき塾では「とにかく書いてごらん」と声をかけます。書いてくれたものがあれば、それを材料に一緒に考えられる。何より、「前の自分が何を考えていたか」を後から見返せることが、最大の財産になります。“空欄”は沈黙です。でも、“ミス”は語ります。だからこそ、「間違いを残す勇気」こそ、学びの第一歩なのです。

「なんで間違えたんだろう」
そう思った瞬間から、子どもの学びは始まっています。ミスとは“できなかった証”ではなく、「何かがズレている」ことに気づく機会です。そこにこそ、成長のヒントが詰まっています。
子どもが「間違った理由」を考えるとき、頭の中ではいくつもの思考が交錯します。
「引っかかったのはここだったかも」
「この言葉、ちゃんと読めてなかったな」
「こういう問題、前も苦手だったような……」
これらはすべて、自己修正のプロセスです。正解をただ覚えるだけでは得られない、“理解の深まり”がそこにあります。
けれどこのプロセスには、必ず“痛み”が伴います。間違えたことを認めるのは悔しいし、恥ずかしい。ときには、「やっぱり自分はダメだ」と落ち込むこともある。でも、それでも立ち止まらずに考えようとすること。それが、「学ぶ」という行為そのものです。
だから私たちは、「間違えていい」と伝えるだけでなく、「間違えたことを見つめ直す力」を育てたいと考えています。
見直す勇気。振り返る根気。そこにこそ、点数や結果以上の“学力”があります。
そしてなにより大切なのは、ミスをした子どもを、責めずに見守るまなざしです。「どこがわからなかった?」「何と間違えたのかな?」と、一緒に考えてあげることで、子どもは“痛み”の中に安心を見つけます。
子どもは、間違いながら育っていきます。その“間違い方”こそが、唯一無二の学びの履歴なのです。

「学校でミスすると、恥ずかしい」
「家庭では、間違いを見せたくない」
——そう感じている子は、実はとても多いのです。
だからこそ、塾という“第三の場”に求められるのは、“安心して間違えられる環境”ではないでしょうか。
私たち、あかつき塾が大切にしているのは、**「正解を教えること」よりも、「自分で気づけるよう導くこと」**です。
子どもたちの間違いに対して、すぐに「違うよ」と言うのではなく、「どうしてそう考えたの?」「他のやり方あるかな?」と問い返す。その一つひとつの対話が、“学びの自走力”を育てる土台になります。
そして、それができるためには、**「失敗しても安心な空気」**が絶対に必要です。笑われない。否定されない。比べられない。そんな場所でこそ、子どもたちは“本当の自分”を出せるようになります。
また、私たちがミスに注目するのは、ただ「できない部分を探す」ためではありません。そのミスの背景には、**「どんな理解のズレがあるか」「思考の癖はどこか」**という情報が詰まっているからです。
ミスとは、**指導者にとっての貴重な“フィードバックデータ”**でもあります。それを無視して正解だけ追い求める教育では、子どもの“伸びる芽”は見落とされてしまうのです。
間違いがあったからこそ、その子にしかない“次の一歩”が見えてくる。だからこそ私たちは、**「よく間違えたね」「ここでつまずけて良かったね」**と声をかけます。
子どもが安心して間違えられる場所。それが、私たちが目指す塾の姿です。

ミスをして落ち込むこと。間違えた自分が嫌になること。やる気をなくして、ノートを閉じてしまう日があること。……全部、あっていいんです。
大人だって、失敗は怖い。子どもなら、なおさらです。
でも、その「怖い」を乗り越えたとき、子どもは確実に一歩、前に進んでいます。
子どもが間違えたとき、大人ができることはひとつです。「大丈夫だよ。よく気づけたね」と言ってあげること。
正解よりも、「なぜ間違えたか」を一緒に考える。それだけで、子どもは“ミス=悪”という呪縛から解放されます。
間違いは、成長の前兆です。“わからない”を“わかる”に変える、その途中にあるものです。そしてその過程こそが、「学ぶ」ということの本質なのです。
私たちは、子どもたちのすべてのミスに意味があると信じています。どんな間違いも、どんな遠回りも、「考えた」という証拠です。
だからこそ、ミスを恐れず、空欄を作らず、自分の考えを言葉にして、紙に書いて、ぶつけてほしい。そうやって重ねた“間違いの記録”が、いつかきっと、「わかる喜び」や「できた自信」に変わっていくから。
ミスは、悪じゃない。
その言葉が、これを読んだ誰かの心に残ってくれたなら、それはもう、小さな“学びの始まり”です。

山本剛義
茨城県つくば市在住。オンライン学習塾「あかつき塾」塾長。公共事業・環境整備・清掃業・ビルメンテナンス業・警備業など幅広く事業展開。子どもたちへの基礎学力支援をライフワークとし、「読み・書き・そろばん」の重要性を提唱している。